「派遣社員だから有給休暇は取れない」 「有給休暇を取ると、次の契約更新に響くのでは…?」 「派遣先から有給を取るなと言われたけど、どうしたらいいの?」
もしあなたが派遣社員として働いていて、上記のような疑問や不安を抱えているなら、このブログ記事はあなたのためのものです。結論から言うと、派遣社員も正社員と同じように有給休暇を取得する権利があります。 労働基準法によって定められた、すべての労働者に与えられた重要な権利なのです。
しかし、派遣という働き方特有の事情から、有給休暇の取得に関して誤解やトラブルが生じやすいのも事実です。この記事では、派遣社員の有給休暇に関するあらゆる疑問を解消し、あなたが安心して、そして賢く有給休暇を活用できるよう、その取得条件から具体的な申請方法、万が一のトラブル時の対処法まで、徹底的に解説していきます。
あなたの権利を守り、より充実したワークライフバランスを実現するために、ぜひ最後までお読みください。

1.有給休暇の基本を知ろう:あなたの権利を理解する第一歩
まず、派遣社員であるかどうかにかかわらず、すべての労働者に共通する有給休暇の基本的なルールについて確認しておきましょう。
1.有給休暇(年次有給休暇)とは?
有給休暇とは、労働者が心身の疲労を回復し、ゆとりのある生活を保障するために与えられる休暇のことです。正式名称は「年次有給休暇」といい、この休暇を取得しても賃金が減額されることはありません。つまり、「休んでも給料がもらえる」のが有給休暇なのです。
2.有給休暇の付与条件と日数
労働基準法第39条により、有給休暇が付与されるには以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 雇入れの日から6ヶ月継続勤務していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤していること
この2つの条件を満たせば、正社員、契約社員、パートタイマー、そして派遣社員も例外なく有給休暇が付与されます。
付与される日数は、勤続年数によって以下のように増えていきます。
| 勤続期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
(週所定労働時間が30時間以上、または週所定労働日数が5日以上の労働者の場合)
週の所定労働日数が少ないパートタイム労働者などには、労働日数に応じた比例付与が適用されます。派遣社員の場合も、週の勤務日数や時間によって付与日数が変わる可能性がありますので、ご自身の契約内容と照らし合わせて確認が必要です。
3.有給休暇の時効と賃金
付与された有給休暇には2年間の時効があります。例えば、2024年4月1日に付与された有給休暇は、2026年3月31日までに取得しないと消滅してしまいます。せっかくの権利を無駄にしないよう、計画的に消化することが大切です。
有給休暇を取得した際の賃金については、以下のいずれかの方法で計算されます。
- 平均賃金:過去3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数で割った金額
- 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金:普段通りの給料
- 健康保険の標準報酬日額(労使協定がある場合)
一般的には「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」が適用されることが多いですが、念のためご自身の派遣会社に確認しておくと安心です。

2.派遣社員特有の有給休暇事情:誤解を解消し、正しい知識を身につける
派遣社員が有給休暇について考える上で、最も重要なポイントは「誰から有給休暇が付与されるのか」という点です。
1.有給休暇の付与元は「派遣会社」
派遣社員は、実際に働く「派遣先企業」と雇用契約を結んでいるわけではありません。雇用契約を結んでいるのは、あなたを派遣している**「派遣会社(派遣元)」**です。
したがって、有給休暇を付与し、管理するのも、そして有給休暇の申請を受け付けるのも、すべて派遣会社になります。この点を理解しておくことが、有給休暇をスムーズに取得する上で非常に重要です。
2.派遣先が変わっても有給休暇は引き継がれる
「派遣先が変わったら、また有給休暇の条件を満たすまで待たないといけないの?」 いいえ、そんなことはありません。
派遣社員の有給休暇は「派遣会社」との雇用契約に基づいて発生するため、派遣先が変わっても、同じ派遣会社との雇用契約が継続している限り、それまでに発生した有給休暇は引き継がれます。 派遣会社に登録した日が「雇入れの日」となり、そこから継続して勤務しているとみなされるのです。
3.契約期間の空白期間と継続勤務の考え方
派遣社員の場合、契約期間が終了し、次の派遣先が決まるまでに一時的に仕事がない「空白期間」が生じることがあります。この空白期間が有給休暇の継続勤務にどう影響するのか、不安に感じる方もいるでしょう。
労働基準法では、1ヶ月以内の空白期間であれば、継続勤務とみなされるとされています。つまり、派遣契約と派遣契約の間に1ヶ月以内のブランクがあっても、有給休暇の付与条件である「6ヶ月継続勤務」のカウントは途切れないということです。
ただし、これは「派遣会社との雇用契約が継続している」ことが前提です。派遣契約が終了するたびに、派遣会社との雇用契約も完全に終了している場合は、その都度「雇入れの日」がリセットされてしまう可能性があります。ご自身の雇用契約がどのように扱われているか、派遣会社に確認することが大切です。
4.派遣社員にまつわる「よくある誤解」を否定
- 「派遣だから有給はない」:これは完全に誤りです。労働基準法はすべての労働者に適用され、派遣社員も例外ではありません。
- 「派遣先の都合で休んだ日は有給にならない」:これも誤解です。派遣先の都合で業務がなくなった場合でも、それは労働者の責任ではないため、労働日としてカウントされ、有給休暇の出勤率にも影響しません。むしろ、派遣先が休業手当を支払う義務が生じるケースもあります。
これらの誤解に惑わされず、あなたの権利をしっかりと主張しましょう。

3.派遣社員が有給休暇を取得する手順:スムーズな申請のために
有給休暇を取得する権利があることは分かりました。では、実際にどのように申請すれば良いのでしょうか。
1. 取得条件の確認(派遣会社への確認)
まずは、ご自身が有給休暇の付与条件を満たしているか、そして何日分の有給休暇が残っているかを派遣会社に確認しましょう。派遣会社の担当営業や、専用のマイページなどで確認できることが多いです。
2. 取得申請の仕方:派遣会社が窓口
有給休暇の申請は、必ず派遣会社に対して行います。 派遣先の担当者に直接伝えるのはマナー違反ではありませんが、正式な申請は派遣会社を通じて行うのがルールです。
- 派遣会社の担当営業に連絡:電話やメール、派遣会社のシステムを通じて、有給休暇を取得したい旨を伝えます。
- 取得希望日を伝える:具体的な取得希望日を伝えましょう。できれば、いくつか候補日を挙げておくと、業務調整がしやすくなります。
- 派遣先への事前相談:派遣会社を通じて、派遣先の担当者にも有給休暇の取得希望日を伝えてもらい、業務に支障が出ないか確認してもらいましょう。業務の引き継ぎなど、必要な調整を行うためです。
派遣会社によっては、独自の申請フォームやシステムがある場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
3.時季変更権について:拒否ではない
有給休暇は原則として、労働者が希望する日に取得できます。これを「時季指定権」といいます。しかし、派遣会社(使用者)には「時季変更権」という権利があります。
時季変更権とは、労働者が指定した日に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、他の日に変更してもらうよう求めることができる権利です。
重要なのは、これは「有給休暇の取得を拒否する」権利ではない、ということです。 あくまで「別の日に変更してほしい」とお願いする権利であり、代替日を調整する義務があります。
- 「事業の正常な運営を妨げる場合」とは?
- その日に休むと、他の誰もその業務を代わることができず、会社の業務が完全にストップしてしまうような、ごく限られたケースです。
- 単に「忙しいから」「人手が足りないから」といった理由では、時季変更権は認められません。
- 特に派遣社員の場合、派遣先が「忙しいから休まないでほしい」と派遣会社に伝えてくることがありますが、それが直ちに時季変更権の行使理由になるわけではありません。派遣会社が代替要員を手配できるか、業務の調整が可能かなどを検討する必要があります。
もし派遣会社から時季変更を求められた場合は、その理由を具体的に確認し、代替日について話し合いましょう。
4.計画的付与制度:会社が指定する有給休暇
有給休暇の中には、「計画的付与制度」によって、会社が取得日を指定できるものもあります。これは、労使協定(労働者と会社の間で結ばれる協定)がある場合に限り、有給休暇のうち5日を超える部分について、会社が取得日を定めることができる制度です。
例えば、夏期休暇や年末年始休暇の一部を有給休暇として消化する、といったケースがこれにあたります。派遣社員の場合も、派遣会社がこの制度を導入していれば、適用される可能性があります。

4.有給休暇取得時のトラブルと対処法:あなたの権利を守るために
有給休暇の権利があることは分かっていても、実際に取得しようとすると様々なトラブルに直面することがあります。ここでは、よくあるトラブルとその対処法について解説します。
1. 「有給を取らせてもらえない」場合の対処法
最も多いトラブルの一つが、有給休暇の申請を事実上拒否されるケースです。
- 派遣会社からの拒否:「今忙しいから」「人手が足りないから」といった理由で、具体的な代替日も提示せずに有給休暇の取得を認めない。
- 派遣先からの圧力:派遣先の担当者から「休まれると困る」「契約更新に響く」といったプレッシャーをかけられる。
このような場合、以下のステップで対処しましょう。
- まずは派遣会社に再確認・交渉
- 「有給休暇は労働者の権利であり、原則として希望する日に取得できる」ことを伝え、改めて取得希望日を伝えます。
- 時季変更権を行使する正当な理由があるのか、具体的に説明を求めましょう。単なる「忙しい」では認められません。
- 業務の調整や引き継ぎについて、具体的にどうすれば良いか相談し、協力する姿勢を見せることも大切です。
- 書面での申請の重要性
- 口頭でのやり取りだけでは、「言った」「言わない」の水掛け論になりがちです。
- メールや派遣会社のシステムを通じて申請履歴を残すようにしましょう。
- もし口頭で拒否された場合でも、その内容をメールで「〇月〇日の有給休暇申請について、〇〇様より〇〇という理由で時季変更(または拒否)のご連絡をいただきましたが、改めて申請させていただきます」といった形で記録に残すことが重要です。
- 労働基準法を盾にする
- 有給休暇は労働基準法で定められた権利です。派遣会社が正当な理由なく有給休暇の取得を拒否することは、労働基準法違反となります。
- この点を派遣会社に伝えることで、対応が変わる可能性があります。
2. 「派遣先から嫌がらせを受ける」場合の対処法
有給休暇を取得したことで、派遣先から冷たい態度を取られたり、嫌味を言われたり、業務を減らされたりといった「嫌がらせ」を受けるケースも残念ながら存在します。
- すぐに派遣会社に相談
- このような状況は、派遣会社の担当営業にすぐに報告しましょう。
- 派遣会社には、派遣社員が派遣先で不当な扱いを受けないよう、適切な措置を講じる義務があります。
- 具体的な状況(いつ、誰から、どのような言動があったか)を詳細に伝え、改善を求めましょう。
- ハラスメントの可能性
- 有給休暇の取得を理由とした嫌がらせは、パワーハラスメントに該当する可能性があります。
- 状況が改善されない場合は、後述する外部の相談窓口への相談も検討しましょう。
3. 「契約更新に影響するのでは?」という不安
有給休暇を取得することで、派遣会社や派遣先からの評価が下がり、契約更新に不利になるのではないかという不安は、派遣社員が有給休暇の取得をためらう大きな理由の一つです。
しかし、有給休暇の取得を理由として、労働者に不利益な取り扱いをすることは、労働基準法や労働者派遣法で明確に禁止されています。
- 労働基準法第136条:「使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」
- 労働者派遣法第30条の5:「派遣元事業主は、派遣労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、当該派遣労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。」
具体的には、有給休暇の取得を理由に、以下のような不利益な取り扱いは許されません。
- 契約を更新しない
- 契約期間を短縮する
- 賃金を減額する
- 不当な配置転換を行う
- 昇給・昇進で不利に扱う
もし、有給休暇の取得を理由に不利益な扱いを受けたと感じたら、その証拠(メール、会話の記録など)を保全し、派遣会社に抗議するとともに、外部の相談窓口に相談することを強くお勧めします。
4. 退職時の有給消化(買い取りの可否)
退職が決まった際、残っている有給休暇をすべて消化したいと考えるのは当然のことです。
- 原則として、有給休暇の買い取り義務はない
- 会社には、労働者が退職する際に残っている有給休暇を買い取る義務は、法律上ありません。
- ただし、会社が任意で買い取ることは可能です。就業規則などで買い取りの規定がある場合もあります。
- 退職時の有給消化は可能
- 退職日までの期間に有給休暇が残っていれば、その期間を有給休暇として消化し、退職することができます。
- 退職の意思を伝える際に、残っている有給休暇の日数を確認し、消化希望日を派遣会社に伝えましょう。
- 引き継ぎ期間などを考慮し、早めに相談することがスムーズな消化につながります。

5.困ったときの相談先:一人で抱え込まず、プロの力を借りよう
派遣会社との交渉がうまくいかない、不当な扱いを受けていると感じるなど、有給休暇に関するトラブルで困ったときは、一人で抱え込まずに外部の専門機関に相談しましょう。
1. 労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準法などの労働関係法令が守られているかを監督する行政機関です。労働基準法違反の疑いがある場合、調査や指導を行ってくれます。
- 相談内容の例:
- 正当な理由なく有給休暇の取得を拒否された
- 有給休暇の取得を理由に不利益な扱いを受けた
- 有給休暇の賃金が正しく支払われない
最寄りの労働基準監督署の窓口に直接行くか、電話で相談できます。
2. 総合労働相談コーナー
都道府県労働局や全国の労働基準監督署内に設置されている相談窓口です。労働問題全般について、無料で相談できます。専門の相談員が、相談内容に応じて適切な情報提供や助言、あっせんなどのサポートをしてくれます。
- 相談内容の例:
- 有給休暇の取得方法が分からない
- 派遣会社とのトラブル全般
- ハラスメントに関する相談
匿名での相談も可能ですので、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
3. 弁護士、社会保険労務士
より専門的なアドバイスや、法的な手続きが必要な場合は、弁護士や社会保険労務士に相談することを検討しましょう。
- 弁護士:労働問題に関する訴訟や交渉代理など、法的な紛争解決をサポートします。
- 社会保険労務士:労働法に関する専門家で、労働基準法に関する相談や、会社との間に入って解決をサポートしてくれます。
費用がかかる場合がありますが、無料相談を受け付けている事務所もあります。
4. 労働組合
もし、あなたが所属している派遣会社に労働組合がある場合、組合に相談することも有効な手段です。労働組合は、労働者の権利を守るために会社と交渉する役割を担っています。

6.有給休暇を賢く活用するメリット:心身ともに健康な働き方のために
有給休暇は単に「休む」だけのものではありません。賢く活用することで、派遣社員であるあなた自身にも、そして派遣会社や派遣先にも、多くのメリットをもたらします。
1.派遣社員にとってのメリット
- 心身のリフレッシュ、ストレス軽減
- 日々の業務で蓄積された疲労やストレスを解消し、心身の健康を保つことができます。リフレッシュすることで、仕事へのモチベーションも向上します。
- プライベートの充実、自己投資
- 旅行に出かけたり、趣味に没頭したり、家族や友人と過ごす時間を増やしたりと、プライベートを充実させることができます。
- また、資格取得のための勉強やセミナー参加、転職活動など、自己投資のためのまとまった時間を確保することも可能です。
- 健康維持と病気の予防
- 定期的な休息は、病気の予防にもつながります。体調が優れないときに無理して出勤し、症状を悪化させることを避けることができます。
- ワークライフバランスの向上
- 仕事とプライベートのバランスが取れることで、生活全体の満足度が向上し、より充実した日々を送ることができます。
2.派遣会社・派遣先にとってのメリット
「派遣社員が有給を取ると、派遣先が困るのでは?」と心配する声もありますが、実は派遣社員が有給休暇を適切に取得することは、派遣会社や派遣先にとってもメリットがあります。
- 社員のモチベーション向上、定着率アップ
- 有給休暇が取得しやすい環境は、派遣社員の満足度を高め、モチベーション向上につながります。結果として、優秀な人材の定着率が高まり、長期的な関係を築きやすくなります。
- 生産性の向上
- リフレッシュした状態で仕事に戻ることで、集中力や生産性が向上します。疲労が蓄積した状態で無理に働くよりも、結果的に質の高い仕事につながります。
- 法令遵守、企業の社会的責任
- 有給休暇の取得を促進することは、労働基準法を遵守し、企業の社会的責任を果たすことになります。これにより、企業のイメージアップにもつながります。
- 業務の属人化防止
- 有給休暇で休むことで、他の社員がその業務を代行する機会が生まれます。これにより、業務の属人化を防ぎ、チーム全体のスキルアップや業務の標準化を促進する効果も期待できます。

まとめとこれからの派遣社員の働き方
このブログ記事を通じて、派遣社員の有給休暇に関する疑問や不安が解消されたことを願っています。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 派遣社員も正社員と同じように有給休暇を取得する権利があります。
- 有給休暇の付与元は「派遣会社」であり、派遣先が変わっても有給休暇は引き継がれます。
- 申請は派遣会社を通じて行い、派遣先への事前相談も忘れずに。
- 正当な理由なく有給休暇の取得を拒否されたり、不利益な扱いを受けたりすることは違法です。
- 困ったときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなど、外部の専門機関に相談しましょう。
有給休暇は、あなたが健康で充実した生活を送るために、そして長く安定して働くために不可欠な権利です。この権利を正しく理解し、積極的に活用することで、あなたのワークライフバランスは大きく向上するでしょう。
もし、今あなたが有給休暇の取得で悩んでいるなら、この記事で得た知識を武器に、ぜひ一歩踏み出してみてください。あなたの権利を守り、より良い働き方を実現するために、私も応援しています。
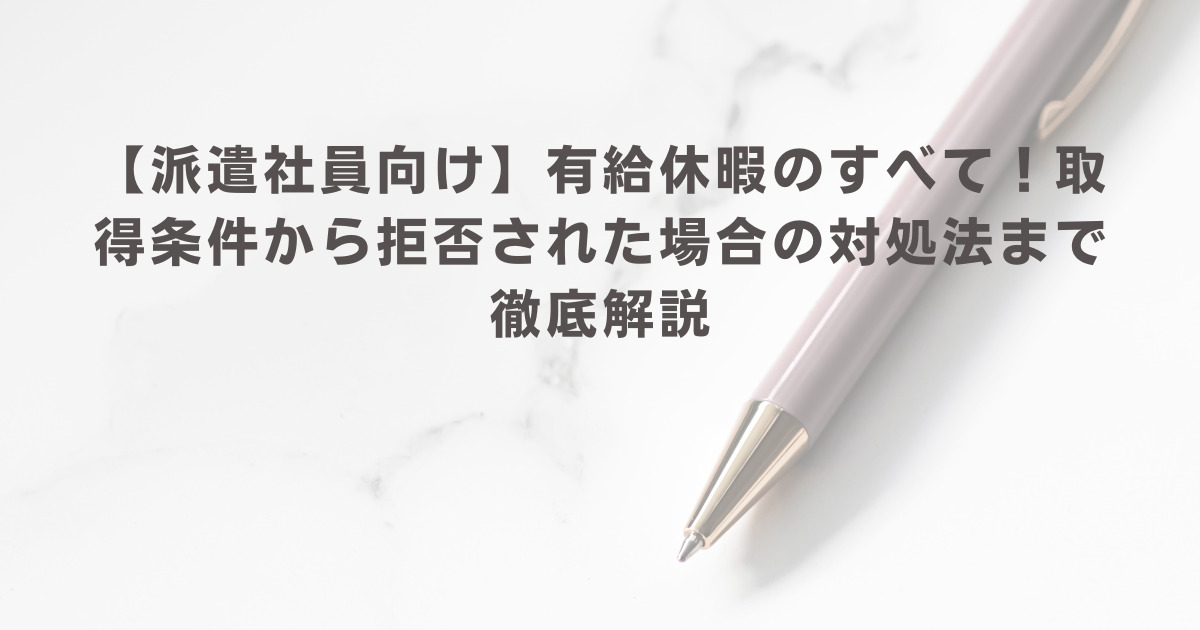
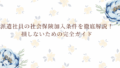
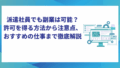
コメント