「もうすぐ60歳だけど、派遣の仕事は続けられるのかな?」
「3年ルールがあるから、一つの会社で長く働けないのでは…」
人生100年時代と言われる現代、60歳を迎えてもなお「自分らしく働きたい」と願う方は増えています。しかし、派遣社員として働く方にとって、一つの職場で長く働き続けられない「3年ルール」は、大きな不安材料の一つかもしれません。
実は、60歳以上の派遣社員には、この「3年ルール」が適用されないという、非常に重要な例外規定があることをご存知でしょうか?
この記事では、60歳以上で派遣社員として働く、またはこれから働こうと考えている方に向けて、
- 派遣社員の**「3年ルール」の基本**
- なぜ60歳以上が例外となるのか、その法的根拠
- 60歳からの派遣社員という働き方がもたらすメリット・デメリット
- 安定して長く働き続けるための具体的なコツ
について、徹底的に解説していきます。この記事を読めば、あなたのキャリアに対する不安が解消され、未来への一歩を踏み出す勇気を得られるはずです。ぜひ最後までお読みいただき、今後の働き方の参考にしてください。

1:派遣社員の「3年ルール」とは?基本をおさらい
まず、60歳以上の例外規定を理解する前に、派遣社員の「3年ルール」の基本についておさらいしましょう。
「3年ルール」とは、正式には**「労働者派遣法に基づく派遣期間の制限」**のことです。このルールには、大きく分けて2つの側面があります。
- 事業所単位の期間制限(派遣先の同一事業所での制限)
- 派遣社員を受け入れる企業(派遣先)は、原則として、同じ事業所で派遣社員を3年を超えて受け入れることはできません。
- 正確には、同一の派遣先の事業所が派遣社員を受け入れることができる期間は最長3年であり、これを超える場合は過半数労働組合等からの意見聴取が必要となります。
- この制限は「事業所単位」で適用されるため、ある派遣社員の契約が3年で終了しても、別の派遣社員を受け入れることは可能です。
- 個人単位の期間制限(同一の派遣社員での制限)
- 派遣社員は、原則として、同じ派遣先の組織単位(課やグループなど)で3年を超えて働くことはできません。
- たとえば、あなたがA社のB課で派遣社員として働いている場合、B課で働ける期間は最長3年となります。
- この制限は「個人単位」で適用されるため、3年が経つと、あなたは原則としてその組織単位(B課)で働くことはできなくなります。
この2つのルールは、派遣社員が安定した雇用を得られるように、派遣先が派遣社員を安易に使い続けるのではなく、直接雇用を促すことを目的としています。
1.3年ルールを回避して働き続けるには?
「3年経ったら、必ず退職しなきゃいけないの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、いくつかの例外や方法があります。
- 派遣先企業での直接雇用:
- 派遣期間中に派遣先企業の正社員や契約社員として直接雇用されるパターンです。これが最も理想的なケースと言えるでしょう。
- 派遣先事業所内での異動:
- 派遣期間の制限は「組織単位」に適用されるため、同じ派遣先企業であっても、別の部署(課やグループ)へ異動すれば、また新たに3年間の派遣期間がスタートします。ただし、異動の可否は派遣先企業の状況によります。
- 無期雇用派遣:
- 派遣会社と期間の定めのない雇用契約を結ぶ「無期雇用派遣」で働く場合は、3年ルールの対象外となります。この働き方については後ほど詳しく解説します。
- 60歳以上の派遣社員:
- そして、この記事の主題である「60歳以上の派遣社員」も、この3年ルールの例外となります。

2:なぜ60歳以上の派遣社員に「3年ルール」が適用されないのか?
それでは本題です。なぜ、60歳以上の派遣社員は「3年ルール」の適用外となるのでしょうか?その根拠は**「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)」**に明確に定められています。
労働者派遣法の第四十条の三には、以下の例外規定が明記されています。
“前条から前三条までの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する派遣労働者に係る労働者派遣については、期間制限の適用がないものとする。”
(中略)
“六十歳以上の者”
この条文からもわかるように、60歳以上の派遣労働者は、労働者派遣法の期間制限(3年ルール)から除外されています。これは、労働者派遣法が改正された際に、高齢者の雇用機会を確保し、安定した働き方を支援するために設けられた重要な規定です。
1.60歳以上とは具体的にいつから?
この「60歳以上」という条件は、60歳の誕生日を迎えた日以降に適用されます。
たとえば、59歳で派遣社員として働き始めた方が、働いている途中で60歳になった場合、その時点から3年ルールの制限はなくなります。これにより、同じ派遣先で3年を超えて働き続けることが可能になります。
2.この例外規定が生まれた背景
なぜ、このような例外が設けられたのでしょうか。その背景には、国が推し進める**「高齢者雇用の安定」**という大きな目的があります。
少子高齢化が急速に進む日本では、労働人口の減少が深刻な課題となっています。その一方で、健康で働く意欲のある高齢者が増えています。定年延長や継続雇用制度も広まっていますが、必ずしもすべての人が同じ企業で働き続けられるわけではありません。
こうした状況で、多様な働き方の一つである「派遣」という選択肢が、高齢者にとって有効な選択肢となり得るのです。もし高齢者にも3年ルールが適用されれば、せっかく身につけたスキルや経験を活かせる職場を3年ごとに変えなければならず、不安定な働き方になってしまいます。
そこで、労働者派遣法を改正し、60歳以上の方々が自身のスキルや経験を活かして、安定的に働き続けられるよう、特別に期間制限の適用外としたのです。

3:60歳からの派遣社員の働き方【メリット・デメリット】
60歳を過ぎてから派遣社員として働くことには、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。ここでは、具体的に見ていきましょう。
1.60歳からの派遣社員のメリット
- 長期的な就業が可能
- 3年ルールの適用外であるため、あなたのスキルや経験、人柄が派遣先企業に評価されれば、長期にわたって同じ職場で働き続けることができます。雇用期間の不安が解消されるため、安心して業務に専念できるのは大きなメリットです。
- これまでの経験・スキルを活かせる
- あなたは60年以上の人生で、様々な経験を積んでこられました。これは、若い世代にはない最大の強みです。長年のキャリアで培った専門的な知識やスキル、マネジメント能力、コミュニケーション能力などを活かせる仕事が豊富にあります。特に、企業が若手社員の育成を必要としている場合、あなたの経験は非常に重宝されるでしょう。
- ワークライフバランスを重視できる
- 派遣という働き方は、勤務時間や勤務日数、残業の有無などを、ある程度自分で選ぶことができます。たとえば、「週に3日だけ働きたい」「午前中だけの仕事がいい」といった希望を、派遣会社のコーディネーターに相談することが可能です。これにより、仕事とプライベート、家族との時間を両立させながら、無理のない範囲で働くことができます。
- 専門性を活かし、スキルアップも
- これまでのキャリアとは異なる分野に挑戦したい場合でも、派遣は有効な手段です。未経験の仕事でも、研修制度が充実した派遣会社を選べば、新しいスキルを身につけるチャンスがあります。また、様々な職場を経験することで、常に新しい刺激を受け、自身のスキルをブラッシュアップし続けることができます。
- 多様な働き方の選択肢
- 年金を受給しながら、少しだけ生活の足しにしたいという方もいるでしょう。あるいは、第二のキャリアとして本格的にフルタイムで働きたいという方もいるかもしれません。派遣は、あなたの希望に応じて働き方を柔軟に調整できるため、様々なライフスタイルに合わせた選択が可能です。
2.60歳からの派遣社員のデメリット
- 給与水準が現役時代より下がる可能性
- 多くの60歳以上の派遣社員は、現役時代に正社員として得ていた収入と比較すると、時給換算での給与水準が下がる可能性があります。これは、責任のある役職から離れ、専門職やサポート職に就くことが多いためです。しかし、年金収入と組み合わせることで、生活費を補うという視点で見れば、十分な収入となる場合も多いです。
- スキルアップの機会が限定的
- 正社員と比べると、派遣社員は業務範囲が限定されることが多く、高度なスキルを習得する機会が少ない場合があります。ただし、これは派遣先の企業や業務内容によって大きく異なります。最新の事務ツールやITスキルなどを習得したい場合は、事前に派遣会社の担当者に相談し、スキルアップ支援制度などを活用することも可能です。
- 社会保障や福利厚生が不十分な場合も
- 派遣社員は、正社員と比べて、交通費が自己負担になったり、退職金制度や賞与がないケースが一般的です。また、健康保険や厚生年金などの社会保険は、一定の条件(週20時間以上、月額賃金8.8万円以上など)を満たせば加入できますが、雇用条件によっては加入できない場合もあります。
- 仕事が見つからない「ブランク期間」が発生する可能性
- 派遣の仕事は、契約期間が満了すると、次の仕事が見つかるまで待機期間(ブランク)が発生する可能性があります。特に、特定のスキルや経験が求められる案件では、希望する条件の仕事がすぐに見つからないこともあります。複数の派遣会社に登録し、常に情報収集をすることが重要です。

4:60歳以上が派遣で安定して働き続けるための5つのコツ
デメリットを最小限に抑え、メリットを最大限に活かして、60歳を過ぎても派遣で安定して働き続けるためにはどうすれば良いのでしょうか。ここでは、5つの具体的なコツをご紹介します。
コツ1:自分の強み・スキルを明確にする「キャリアの棚卸し」
長年の社会人経験で培ってきたあなたのスキルは、かけがえのない財産です。まずは、これまでのキャリアを振り返り、自分の強みやスキルを具体的に洗い出しましょう。
- 職務経歴: どのような会社で、どのような仕事をしてきたか。
- 専門スキル: Word、Excel、PowerPointなどのPCスキル、経理知識、語学力など。
- ポータブルスキル: マネジメント力、コミュニケーション能力、課題解決能力、指導力など。
特に、若手社員の育成や、チームの潤滑油となるような「ポータブルスキル」は、多くの企業が求めているものです。自分の強みを明確にすることで、派遣会社のコーディネーターに自信を持ってアピールできますし、適切な案件を紹介してもらいやすくなります。
コツ2:派遣会社を複数登録する
一つの派遣会社だけに頼るのではなく、複数の派遣会社に登録することが、安定して仕事を見つけるための鉄則です。
- 案件数の増加: 会社ごとに保有している求人案件は異なります。複数の会社に登録することで、より多くの選択肢の中から、自分の希望に合った仕事を見つけやすくなります。
- 担当者との相性: 派遣会社の担当者(コーディネーター)は、あなたのキャリアを左右する重要なパートナーです。複数の会社に登録することで、親身になって相談に乗ってくれる、信頼できる担当者を見つけられる可能性が高まります。
- 情報収集: 業界の動向や給与水準、求人市場の状況など、複数の派遣会社から情報を得ることで、より広い視野で仕事探しができます。
コツ3:新しいスキルや知識を学ぶ意欲を示す
「もう60歳だから…」と諦めるのではなく、新しいことを学ぶ意欲をアピールすることは非常に重要です。
たとえば、
- IT化が進む現代では、WordやExcelだけでなく、クラウドサービス(Google Workspaceなど)やオンライン会議ツール(Zoom、Teamsなど)の基本操作ができると、仕事の幅が広がります。
- 派遣会社によっては、これらのスキルを無料で学べるeラーニングを提供しているところもあります。積極的に利用しましょう。
新しい知識を吸収しようとする姿勢は、若い世代の社員にも良い刺激を与え、職場での人間関係を円滑にする上でも役立ちます。
コツ4:年齢を気にしない「柔軟なマインドセット」を持つ
年齢を気にしすぎると、仕事探しや職場の人間関係で壁を感じてしまうことがあります。大切なのは「年齢はただの数字」と捉え、柔軟なマインドセットを持つことです。
- 若手社員との協調性: 職場には、自分より年下の社員が上司やリーダーとして活躍しているケースも珍しくありません。彼らの意見に耳を傾け、敬意を払い、協力して業務を進める姿勢が求められます。
- 謙虚さ: これまでの経験を活かしつつも、「若い人のやり方にはついていけない」と決めつけず、謙虚に新しい知識ややり方を吸収する姿勢が大切です。
年齢を言い訳にせず、柔軟に対応することで、あなたは職場にとってかけがえのない存在になれるでしょう。
コツ5:健康管理を徹底する
60歳を過ぎても長く働き続けるためには、何よりも健康が資本です。
- 適度な運動: 日々の生活にウォーキングやストレッチなどの軽い運動を取り入れましょう。
- バランスの取れた食事: 栄養バランスの取れた食事を心がけ、体調を整えましょう。
- 質の良い睡眠: 質の良い睡眠を確保することは、心身ともに健康を保つために不可欠です。
健康診断を定期的に受けることはもちろん、少しでも体調に異変を感じたら無理をせず、早めに休息を取ることも大切です。

5:無期雇用派遣という選択肢
派遣社員として長期的に安定して働きたいと考える方にとって、無期雇用派遣という選択肢も非常に有効です。
1.無期雇用派遣とは?
無期雇用派遣とは、派遣会社(あなたの雇い主)と期間の定めのない雇用契約を結び、様々な派遣先で働く雇用形態のことです。
通常の派遣(有期雇用派遣)が派遣会社との契約期間に定めがあるのに対し、無期雇用派遣では、派遣先の契約が終了しても、派遣会社との雇用契約は継続します。
2.無期雇用派遣のメリット
- 雇用の安定: 派遣先での契約が終了しても、派遣会社との雇用契約は続くため、給与の支払いが途切れることがありません。待機期間中も給与が支払われるのが大きなメリットです。
- 昇給・賞与の可能性: 派遣会社の社員となるため、昇給や賞与の対象となる場合が多いです。
- 福利厚生の充実: 派遣会社の正社員に準じた福利厚生が受けられることが多く、社会保険や退職金制度なども充実している場合があります。
3.60歳以上でも無期雇用派遣は可能?
はい、可能です。
労働契約法に定められた「無期転換ルール」により、有期雇用で5年を超えて働いた場合、労働者が申し出れば無期雇用に転換することができます。このルールは60歳以上の派遣社員にも適用されます。
また、最初から無期雇用派遣の社員として採用している派遣会社もあります。60歳を過ぎてからでも、専門的なスキルや経験を活かせる無期雇用派遣の求人は増えてきています。
無期雇用派遣は、60歳からの派遣社員が「雇用の安定」を最も手に入れやすい働き方の一つです。派遣会社を選ぶ際には、無期雇用派遣の制度があるかどうかも確認してみることをおすすめします。

まとめ:60歳からの派遣社員は「人生100年時代」の賢い選択肢
この記事では、60歳以上の派遣社員に「3年ルール」が適用されないという事実と、その働き方の具体的なメリット・デメリット、そして安定して働くためのコツについて詳しく解説してきました。
60歳を過ぎてからの派遣社員という働き方は、決して「一時しのぎ」の選択肢ではありません。
- 長年のキャリアで培ったスキルを活かし、社会に貢献できる
- 自分のライフスタイルに合わせて、無理なく働ける
- 3年ルールの制限がなく、安定した雇用を確保できる
これらの大きなメリットを活かせば、60歳を過ぎてからも、自分らしく、イキイキと働き続けることができます。
もちろん、新しい環境に飛び込むことに不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、日本の社会は、健康で働く意欲のあるシニア世代を強く求めています。あなたの経験や知恵は、若い世代にはない貴重な財産です。
「3年ルール」の適用外という規定は、国が60歳以上の方々の再就職・キャリア継続を強く後押ししていることの証でもあります。
この機会に、もう一度ご自身のキャリアプランを見つめ直し、新たな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。この記事が、あなたの未来を切り開くための一助となれば幸いです。
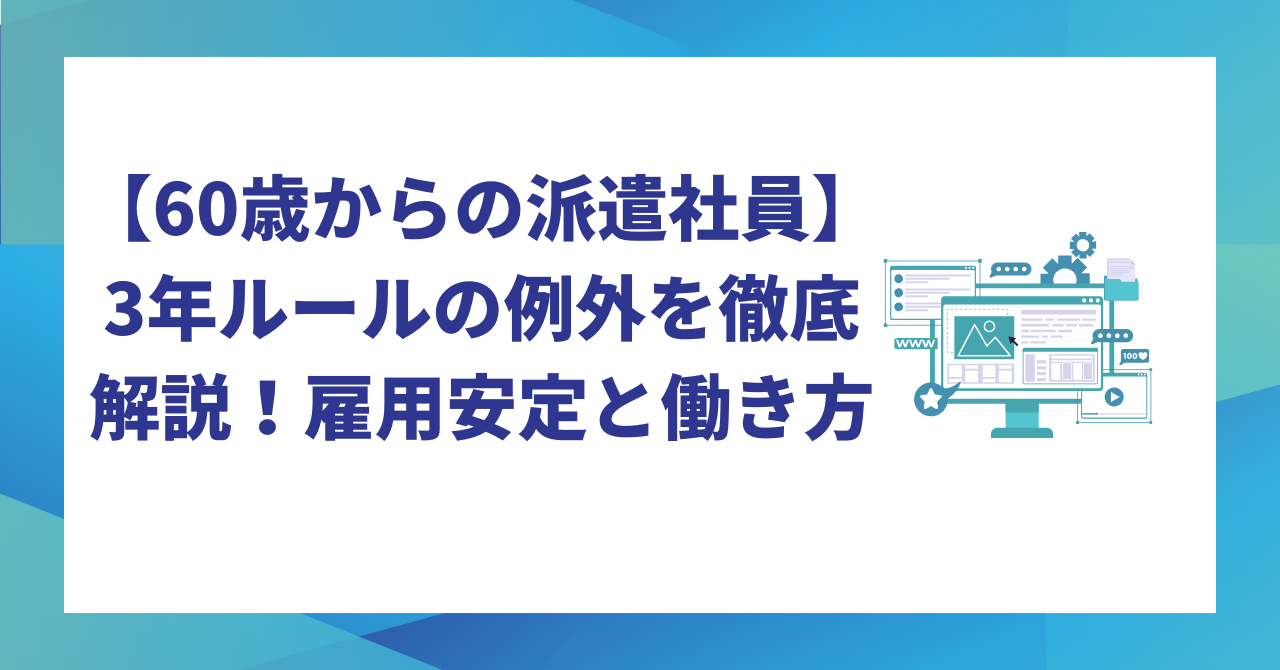
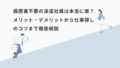
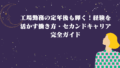
コメント